株初心者のためのNISA講座~NISAの基本から投資戦略まで~

こんにちは。私は福岡の田舎町に妻と子供2人と住む33歳の平凡な会社員です。私は常々『FIRE』に憧れ、55歳で会社を早期退職し、妻とのんびり旅行ライフを夢見て日々邁進しています。
今回は「NISA(少額投資非課税制度)」についてわかりやすく解説します。投資に興味があるけど、どこから始めればいいのか分からないという方にとって、NISAはとても役立つ制度です。さっそく、その基本から実際の運用方法などについて私の実践を交えながら一緒に見ていきましょう!
- NISAってなに?
- NISAの活用方法を知りたい
- 老後の資金を貯めたい
- FIREしてのんびり暮らしたい
NISAの基本知識
NISAとは
まず初めにNISAについて触れておこうと思います。NISAとは国が推奨している少額投資非課税制度のことで、今年(2024年)からNISA制度が新しくなり新NISAが始まると話題にもなりました。実はこの旧NISAから大幅な制度改正が行われたことにより、かなり使いやすいものとなったのです。このことからも国は国民に対してNISA制度を活用して投資を始めて欲しいという思いが伝わりますよね。メディアなどでもかなり取り上げられていますが、なぜここまで国がNISAを推しているかですが、日本は少子高齢化が加速化しており、年金問題やら老後2,000万円問題などこれまで言われてきたように、「これ以上国民の皆さんの老後の面倒は見れない(=年金払えない)。だから、自分たちの老後の資金は自分たちでなんとかしてください。その代わり‼NISAという制度を設けるので、これでなんとかしてください。」と、国が言っている訳なんです。
国がNISAを勧める理由
国がNISAを勧める理由については主に次の3つの目的があります。
- 投資をもっと身近に・・・税金の心配を減らし、投資の魅力を広める。
- 資産形成をサポート・・・少額からの投資を奨励し、資産形成を促進する。
- 経済の活性化・・・投資を通じて経済を活性化させる。
このように、国がNISAを勧める目的に国民の資産形成をサポートしつつ、投資を身近なものに感じて欲しい。そしてより多くの国民の皆さんが投資を始めることにより、経済を活性化させるという狙いがあります。経済が活性化されることにより、株価も全体的に底上げされ、日経平均も上がっていく。こういうシナリオに繋がっていきます。今般、様々な経済アナリストたちが、○○年後には日経平均が10万円に到達‼など騒がれていますが、これの一つの要因として、この流れもあると考えています。ちなみに、今現在(2024年9月時点)株価は4万円弱ですので、数年後には株価が2倍以上になっていると予想されています。
NISAには2種類の投資方法と上限額がある
NISAには2種類の投資方法があり、それぞれに上限額が設定されています。下表をご覧ください。
| 項 目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合 計 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 360万円 |
| 非課税期間 | 無期限可 | 無期限可 | - |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 1,200万円 | 1,800万円 |
このように、”少額投資”とあるように、毎年の投資額に上限額が決められています。ちなみに、最短でNISA枠を満額使い切るためには、30万円/月投資に回す必要があります。このとき、360万円/年になるため、最短5年でNISA枠1,800万円を使い切ることができます。しかし、実際これほどの金額を投資に回せる方は少数だと思います。私も生活費等切り詰めて10万円/月が限界です。
NISAのメリット・デメリット
さて、NISAについて基本的なことはご理解頂けたかと思います。NISAは投資を始めるにあたって非常に有用な制度ですが、メリットだけでなくデメリットもしっかり理解しておくことが大切です。
NISAのメリット
まずメリットについて一緒に見ていきましょう。メリットは主に以下の5つになります。
- 税金がかからない
NISAの最大のメリットは、投資で得た利益が非課税になることです。通常、投資の利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を利用することでその税金が免除されます。これにより、利益をそのまま手に入れることができ、資産形成が加速します。 - 少額から始められる
NISAは少額から投資を始めることができるため、初心者でも手軽に始められます。特に「つみたてNISA」は月々数千円からの積立が可能で、無理なくコツコツと資産を形成することができます。 - 投資対象が多様
新NISAでは、投資対象が広がり、より多くの選択肢から投資先を選ぶことができます。一般NISAでは株式や投資信託、ETF(上場投資信託)など、つみたてNISAでは長期積立向けの投資信託など、幅広い選択肢があります。 - 長期間の非課税運用
新NISAでは、非課税期間が無期限とされているため、長期的な資産形成がしやすくなります。そのため、長期間にわたって運用することで複利の効果を享受しやすくなります。ちなみに、旧NISAでは非課税期限が設けられており、少し運用しづらい点がありましたが、制度改正で撤廃されています。 - 使い道が自由
NISA口座で得た利益は、再投資や生活費、趣味のために使うことができます。資産形成を目的にしたり、投資先を選んだりする自由度が高いのもNISAの魅力の一つです。
NISAのデメリット
次にデメリットについても見ていきましょう。デメリットは以下の4つになります。
- 非課税枠の制限
NISAには年間の非課税枠が設定されており、成長投資枠で360万円/年(満額1,200万円)、つみたて投資枠で120万円/年(満額600万円)といった上限があります。この枠を超えると、その超えた部分には通常の課税が適用されますので、資産を多く運用したい場合には注意が必要です。 - 投資の損失が税金控除に利用できない
少し小難しい話になりますが、NISA口座で発生した損失は、通常の課税口座での利益と相殺することができないため、リスク管理が重要となります。例えば、今年NISAで100万円マイナスになったとします。NISA枠とは別に株式投資を行っていたとして、こっちで100万円プラスになったとします。この時、通常の株式の場合、損益通算といって、マイナスとプラスを相殺できるという仕組みがあるため、この年の損益は0円(=1円も課税されない)となる訳ですが、一方がNISAの場合はこの損益通算が通用しないため、株式投資の収益100万円に約20%課税されてしまう。というものです。かなりややこしいですが、これ実は上級者向けの話ですので、NISAだけ始めるという初心者の方には全く関係ありません。 - 投資先の選定が難しい場合がある
多様な投資対象が選べることはメリットですが、初心者にとってはどの投資商品を選ぶかが難しいこともあります。ここは後ほど実践をお伝えしますので、解決して頂けるかと思います。 - 口座開設の手間
NISA口座を開設するには、証券会社や銀行での手続きが必要です。また、口座の管理や運用には一定の手間がかかります。特に初心者にとっては、この手間が一番デメリットとして感じられるかもしれません。YouTubeに口座開設のやり方など載っていますので、参考にして頂き、なんとかここを乗り切ってください‼このとき、面倒だからといって、銀行の窓口に行くのは絶対やめてください!銀行から余計な手数料を取られるため、ここだけは頑張ってネットで証券口座を開設してください。ここでの頑張りが未来を間違いなく大きく変えます!
NISAの運用方法について
さて、NISAの基本からメリット・デメリットまでご理解頂けたら、あとは実際にどういう風に運用していけば良いのか。一緒に学んでいきましょう。先ほど説明したように、NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠の2種類があるため、それぞれ運用方法は異なります。ただし、同じ方法で運用することも一部可能ですので、詳しく説明していきます。
つみたて投資枠の運用方法
つみたて投資枠では投資できる商品の選択しが限られています。具体的には投資信託とETF(上場投資信託)のみになります。投資信託とは、私たちのお金をプロに預けて代わりに運用してもらうというもので、株の知識がなくてもこれなら安心して投資が可能でしょう。あとはどの投資信託を選ぶかですが、投資信託にもインデックスファンドとアクティブファンドという2種類があります。簡単に言うと、堅実な商品かそうでないかです。もちろん後者の方がリターンは大きいかもしれませんがその分リスクが伴います。どちらを選ぶかは個人の判断ですが、長期で考えるならインデックスがよいと考えます。理由は2つあり、将来○○年後にいくらになっている。という想定が立てやすいのと、インデックスの方が圧倒的に手数料が低いためです。アクティブの場合、プロがいっぱい頑張る分手数料を多く払わないといけません。ここをどう捉えるかは人それぞれですが、アクティブを購入するなら、少なくとも分散投資(インデックス6~8:アクティブ2~4)することをオススメします。有名な格言の一つに『卵は一つの籠に盛るな』というものがあります。これは、一つの籠に卵を全て入れていて、籠を落としてしまったとき、籠の中の卵は全て割れてしまいます。一方、4つの籠に入れていて、一つ籠を落としてしまっても、3/4は助かる。というもので、要は分散しましょうということを表しています。
ここからは私の実際に運用している商品になりますが、私は『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』という投資信託に投資しています。S&P500とは、アメリカの大手企業500社の株式で構成される株価指数で、これに連動した成果を目標としている商品になります。私の主観ですが、世界情勢が今後どうなるかなど誰にも予想はできません。しかし、少なくともアメリカトップの時代がここ何十年で変わることはないと考えています。今後、イスラエル戦争や、コロナのような流行り病などの影響を受け、一時的に暴落する可能性はありえますが、長期で右肩上がりに成長を続けるのは間違いないと思います。まさにNISAで投資するにはうってつけの商品ではないかと考えます。また、日経平均に連動したインデックス商品を選ぶのもアリだと思います。理由は先ほども述べましたが、○○年後には日経平均10万円時代がやってくるからです。○○年後が5年後なのか、10年後なのかは分かりませんが、必ずやってくるのは間違いないと考えています。
成長投資枠の運用方法
成長投資枠で運用できる商品はたくさんあります。先ほどつみたて投資枠でお話した投資信託やETFはもちろんのこと、国内株式や外国株式にも投資が可能になるため、投資戦略の幅が一気に広がります。したがって、ここでの投資戦略が非常に重要になってくると考えます。私の場合は、成長投資枠で日本の個別株に投資しています。理由は主に以下の2つになります。
- 外国株より日本株の方が調べやすい
個別株の銘柄を調べるとき、その会社がどのような事業を行っているのか。決算書をチェックする時や、会社のHPを見て、分かりやすい内容か。など調べるときに外国だともちろん英語だったりするため内容が分かりません。また、自分の身近な企業だからこそ分かることもあります。例えば近くの飲食店で、今まではこどもに対するサービスが充実していたが、あるとき急にそのサービスが廃止されていました。その会社を調べてみると社長が変わって経営方針が変わっていた。ということもがありました。これは、身近で直接足を運べるからこそ気付ける点だと思います。 - 今後の日経平均に期待
何度も述べているように、今後日経平均は2倍以上になると予想しています。今現在が株価が4万円弱のところで推移していますが、年末に掛けて4万円を超えてくると思います。昨年の伸びを考えると5万円近くまで上がるかもしれません。色々勉強していくと、こういったことを日々考えて投資することが楽しいと思えるようになります。この記事を読んで頂けている方は、本業の方が忙しい方ばかりでしょうけど、出来ればこの楽しみを一緒に味わって頂きたいなと思います。
以上のことから、私は成長投資枠では日本の個別株に投資している訳ですが、米国株が良いという方もたくさんいらっしゃいます。その主な理由は、米国は株主還元主義だからです。個別株を購入したとき、購入した金額に対して毎年〇%の配当金(謝礼金みたいなもの)が出ます。この〇%が日本に対して米国の方が明らかに高いという点です。ただ、日本も株主還元主義にしていこうという傾向にありますので、せっかく株始めるなら日本の企業を応援したくありませんか?と私は思いますが、そこは皆さんの判断に委ねることにしましょう。
つみたて投資枠と成長投資枠の投資戦略
さて、2種類の投資枠について学んだところで、これらを活用した投資戦略を立てていきましょう。NISAを活用した投資戦略は大きく2つになります。
- つみたて投資枠【堅実】+成長投資枠【リスク大】
これは私が行っている投資戦略になります。一つの籠で着実にお金を増やしつつ、もう一つの籠でリスクを取ってガッツリお金を増やしていこうというものです。ここで重要なのがこのもう一つの籠をさらに分散していくつもの籠を用意し、リスク回避することで、なるべくお金が減らないようにすることが重要になります。ここのお話は非常に重要になってくるため、別の記事でお伝えします。 - つみたて投資枠【堅実】+成長投資枠【堅実】
本業で忙しくて株の勉強をする暇がない方や、そもそもリスクを取りたくない方はこっちをオススメします。成長投資枠でも投資信託を購入することが可能ですので、つみたて投資枠同様プロにお任せして、着実にお金をふやしていこう。というものになります。
まとめ
今回は「NISA(少額投資非課税制度)」について解説しました。NISAは税制優遇があり、少額から投資を始めやすく初心者には非常に有用な制度ですので、使わないのはもったいないです。今回の記事でNISAのメリットやデメリットをしっかり勉強して頂き、自分に合った投資戦略を練って、将来の老後資金の不安解消や、私のようにFIREを目指して一緒に頑張りましょう。今後も個別株投資の戦略や個別銘柄の選定ポイントなど記事を配信していきますので、また次回お会いしましょう!
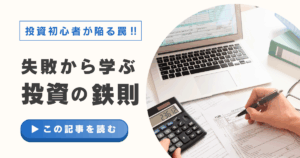
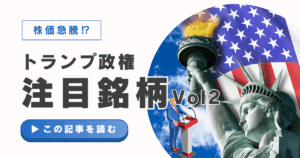
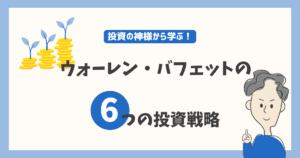
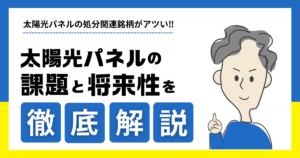



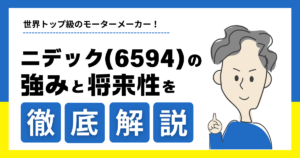
コメント